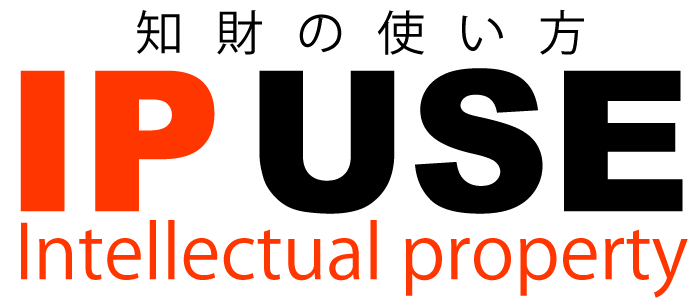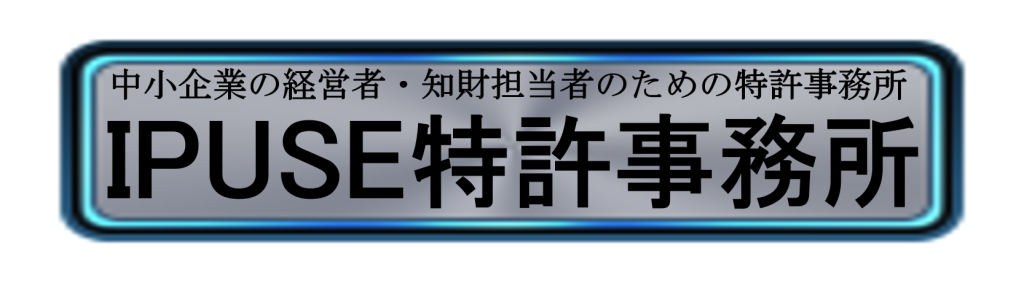独立項と従属項の関係
➡「独立項は従属項に比較して権利範囲が広く、従属項の権利範囲は独立項の権利範囲に包含される。」
この独立項と従属項の関係から、特許実務では次のことがいえます。
| (1)特許権侵害を考えると、独立項だけでもよい(従属項はなくてもよい)。 (2)審査(無効審判を含む)を考えると、従属項はあった方がよい。 (3)従属項が増えると費用がかさむので、必要な従属項だけ特許にする(作っておく)のがよい。 |
まず、「独立項」「従属項」の権利範囲について整理していきます。
例:特許X
【請求項1】a部材を含む、装置
【請求項2】b部材を含む、請求項1に記載の装置
【請求項3】c部材を含む、請求項2に記載の装置
このとき
【請求項1】は独立項
「請求項1に記載の装置」となっている【請求項2】は請求項1の従属項
「請求項2に記載の装置」となっている【請求項3】は請求項2の従属項
となります。
権利範囲は下図のようになります。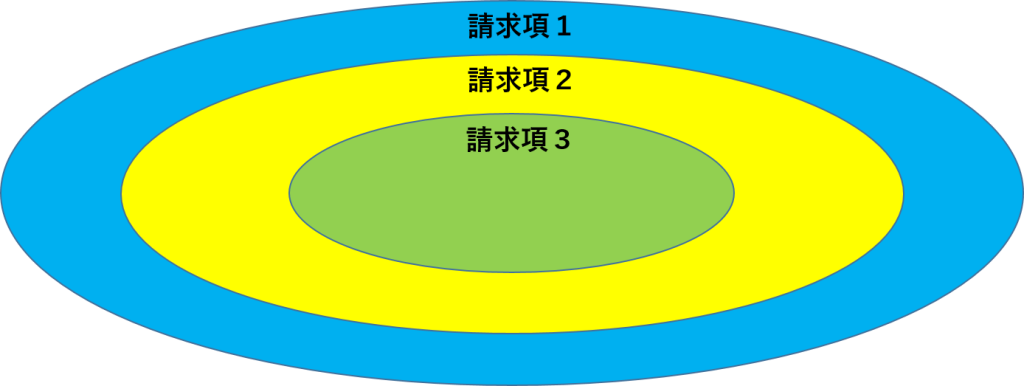 この図から、権利範囲が【請求項1】(独立項)>【請求項2】(従属項)>【請求項3】(従属項)となり、
この図から、権利範囲が【請求項1】(独立項)>【請求項2】(従属項)>【請求項3】(従属項)となり、
【請求項1】は、【請求項2】および【請求項3】を包含し、【請求項2】が【請求項3】を包含していることがわかります。
この例に基づいて
(1)特許権侵害を考えると、独立項だけでもよい(従属項はなくてもよい)。
ということを説明します。
例の特許Xに対して、以下のような製品があったとします。
【イ号物件】a部材を備える(部材b、部材cを備えない)装置。
【ロ号物件】a部材とb部材を備える(部材cを備えない)装置。
【ハ号物件】a部材とb部材とc部材を備える装置。
権利範囲と製品の関係は下図のようになります。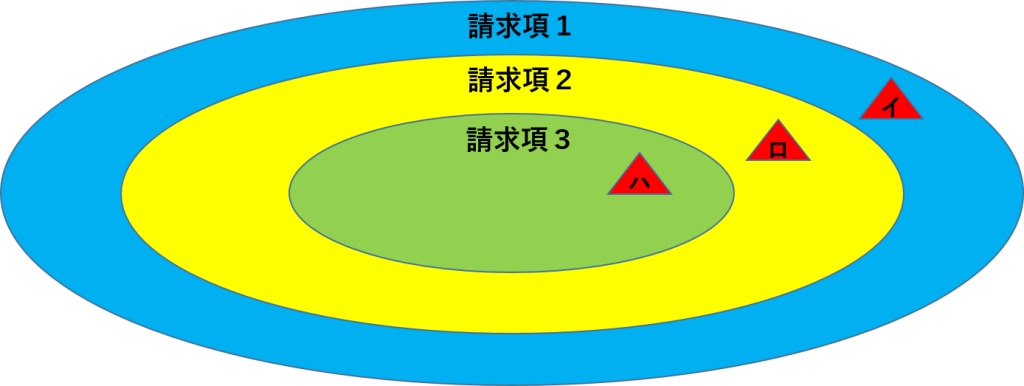
【イ号物件】は【請求項1】のみの侵害となります。
【ロ号物件】は【請求項1】と【請求項2】の侵害となります。
【ハ号物件】は【請求項1】と【請求項2】と【請求項3】の侵害となります。
【請求項1】の権利範囲が広いというのは、多くの侵害品(【イ号物件】【ロ号物件】【ハ号物件】)に権利行使できるということです。
次に権利範囲の広い【請求項2】は、【ロ号物件】【二号物件】に権利行使できます。
権利範囲の一番狭い【請求項3】は、【二号物件】にのみ権利行使できます。
したがって、製品が【請求項2】または【請求項3】を侵害するなら、【請求項1】を侵害することになります。
よって、【請求項1】があれば、【請求項2】または【請求項3】はなくてもかまいません。
このことから、「特許権侵害を考えると、独立項だけでもよい(従属項はなくてもよい)。」ということがわかります。
しかし、審査(無効審判を含む)のことを考えると話はちがってきますので、次に
(2)審査(無効審判を含む)を考えると、従属項はあった方がよい。
ということを説明します。
例の特許Xに対して、審査において以下のような引用文献(の記載)が見つかったとします。
【引用文献A】a部材を備える(部材b、部材cを備えない)装置。
【引用文献B】a部材とb部材を備える(部材cを備えない)装置。
【引用文献C】a部材とb部材とc部材を備える装置。
このとき、権利範囲のイメージでは、下図のようになります。 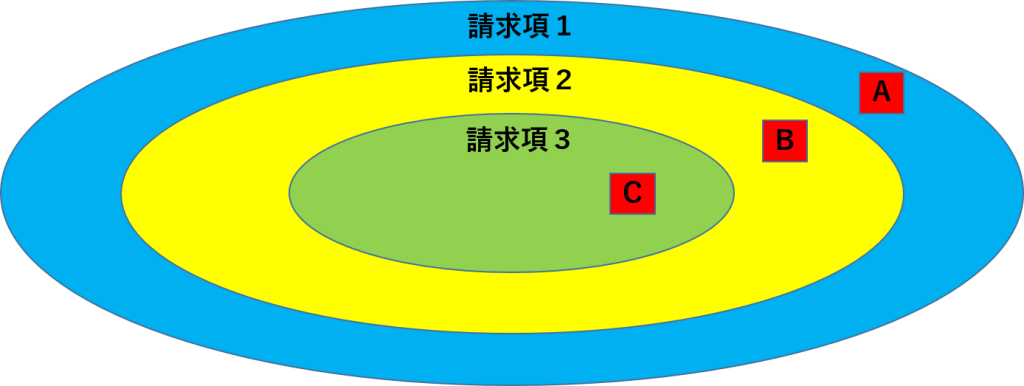 【請求項1】は、【引用文献A】、【引用文献B】、【引用文献C】のどれか1つで拒絶となります。
【請求項1】は、【引用文献A】、【引用文献B】、【引用文献C】のどれか1つで拒絶となります。
【請求項2】は、【引用文献B】、【引用文献C】のいずれか1つで拒絶となります。
【請求項3】は、【引用文献C】で拒絶となります。
【請求項1】の権利範囲が広いというのは、多くの引例
(【引用文献A】、【引用文献B】、【引用文献C】)で拒絶されるということです。
次に権利範囲の広い【請求項2】は、【引用文献B】、【引用文献C】で拒絶になります。
権利範囲の一番狭い【請求項3】は、【引用文献C】にのみで拒絶になります。
【引用文献A】、【引用文献B】が見つかっても【引用文献C】が見つからなければ、【請求項3】は特許になります。
【引用文献A】が見つかっても【引用文献B】が見つからなければ、【請求項2】、【請求項3】は特許になります。
このように、審査の観点では、権利範囲の狭い請求項ほど特許になりやすいといえます。
したがって、特許審査の観点からは従属項【請求項2】、【請求項3】を作るのが普通で、
「(2)審査を考えると、従属項はあった方がよい。」といえます。
(1)と(2)を踏まえて、
(3)従属項が増えると費用がかさむので、必要なものだけ特許にするのがよい。
ということを説明します。
従属項が増えることで、①特許出願費用、②審査請求費用、③登録費用および④維持費用が増えます。
①特許出願費用として、請求項加算等の名称で弁理士費用が増加します。
これは、請求項が1つ増えると10,000円程度増えます。
②審査請求費用として、請求項の増加により特許庁費用が増加します。これは、請求項が1つ増えると4,000円増えます。
③登録費用として、請求項の増加により弁理士費用と特許庁費用が増加します。
これは、請求項が1つ増えると弁理士費用が10,000円程度、特許庁費用が2,700円(1~3年の3年分の費用)増えます。
④維持費用として、請求項の増加により特許庁費用が増加します。これは、特許を15年維持するとして請求項が1つ増えると41,400円(4~15年の12年分の費用)増えます。
これに対して、先に説明したように、従属項は、審査や無効審判において、(独立項に特許性がなくても)特許性を認められることがあります。
先の特許Xの例では、審査において【請求項1】と【請求項2】は拒絶理由があるが、【請求項3】には拒絶理由を発見しない(補正で【請求項1】と【請求項2】を削除すれば特許になるよ)という示唆を含んだ拒絶理由通知がくることがあります。
これが従属項をつくっておく、一番のメリットだと思います。すなわち、発明(【請求項1】~【請求項3】)のどの部分に特許性があるか探りをいれることができ、特許性がわかれば補正も簡単(特許性のないものを削除するだけ)というメリットです。このメリットは、特許になる前の審査のに限らず、特許になった後の審判や侵害訴訟の段階でもあてはまります。
ただし、注意が必要なのは、特許性が認められにくい従属項もあり、従属項ならなんでも作っておけばいいわけではありません。
特許性は、発明の効果で決まりますので、発明特有の効果を持たない従属項は作っても意味がなく、費用の無駄です。
(発明特有の効果があるか否かは従属項をつくった人(主に弁理士)に確認しましょう。)
以上、「経営者・知財担当者なら知っておきたい【独立請求項(独立項)と従属請求項(従属項)の関係】」でした。
| (1)特許権侵害を考えると、独立項だけでもよい(従属項はなくてもよい)。 (2)審査(無効審判を含む)を考えると、従属項はあった方がよい。 (3)従属項が増えると費用がかさむので、必要な従属項だけ特許にする(作っておく)のがよい。 |